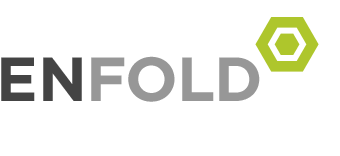ホームページが3か月以上放置される理由を、更新担当者の本音から暴く
ホームページが3か月以上放置される理由を、更新担当者の本音から暴く
気がついたら、前回ホームページを更新したのが「3か月前」だった──。
この現象、実は少なくありません。むしろ中小企業や個人事業主、医療機関などでは「あるある」のように繰り返されています。
ホームページの更新を任されている担当者が「悪いわけではない」のに、更新されないまま時が過ぎていく。いったい何が起きているのでしょうか?
今回は、そんな更新担当者のリアルな「心の声」や「職場の事情」、そしてホームページが放置される構造的な問題に踏み込んでみたいと思います。
■ 本音1:そもそも“何を更新すればいいのか”がわからない
「更新してください」と言われても、ネタがない。
実はこの「ネタがない問題」は、非常に多くの担当者が直面しています。
例えば医療機関であれば、新しい医師の着任情報や休診情報があったときには更新するけれど、それ以外で更新することが思いつかない。
中小企業でも、「製品情報は変わっていない」「イベントもない」「社内の出来事なんて書いていいのかすらわからない」といった声が聞こえてきます。
本当は、社長のつぶやきや、ちょっとした設備の入れ替え、スタッフの何気ないエピソードも“立派な更新ネタ”なのですが、
それを「更新してもいいこと」だと誰も教えてくれなかった。ここに、更新の足が止まる根源があります。
■ 本音2:「時間がない」は“本当”だけど“本質”じゃない
次に多いのが、「忙しくてそれどころじゃない」という本音です。
これは確かに事実で、担当者はたいてい、本業が別にあります。たとえば:
- 総務課の一部としてホームページを管理している
- 医療機関の受付スタッフが片手間で担当している
- 小さな会社の社長自らが“ついでに”見ている
このようなケースでは、ホームページ更新は優先順位の最下層になりがちです。
急ぎの資料作成、社内対応、電話対応、営業事務──。
「今日中にやらなきゃいけない仕事」ではないため、どんどん後回しになります。
ただし、ここで注目したいのは「本当は10分で済むことでも、1週間放置してしまう心理」です。
更新の手順がわからない、過去の更新履歴が引き継がれていない、
画像サイズの指定が面倒、CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)のログイン情報がどこにあるかわからない…。
こういった「小さなストレスの積み重ね」が、更新を“面倒なもの”にしているのです。
■ 本音3:外注先に連絡する“きっかけ”がない
自社で更新できず、制作会社やフリーランスに依頼している場合でも、更新が滞ることはあります。
実際には「ちょっとした変更」をしたいだけなのに、そのためにメールを書いて、資料をまとめて、確認の連絡を受けて…という“手間”が発生します。
しかも、少し時間が経つと「もういいや」と放置してしまう。
また、「このくらいの修正で連絡していいのか」「料金がどれくらいかかるかわからない」「手間取らせたら申し訳ない」といった“心理的なブレーキ”も働きます。
結果として、「連絡するタイミングを失ったまま」数ヶ月が経過することになるのです。
■ 本音4:「デザインが古くて触りたくない」
意外と多いのが、この“気持ちの問題”です。
昔のテンプレートをベースに作られたホームページで、デザインがスマホに最適化されていない、フォントが古臭い、写真が昭和っぽい──。
「なんとなく気恥ずかしくて、見返したくない」
「更新しても、見栄えが良くならないからテンションが上がらない」
こうなると、ホームページ自体が“負の遺産”のような存在になります。
当然、更新する意欲も湧きません。
こういったケースでは、実は「更新の代行」よりも「リニューアル」の方が合理的な解決策だったりもします。
■ 本音5:「CMSが使いづらい」問題と“ブラックボックス化”
WordPress(ワードプレス)などのCMSを導入している企業も多いですが、「うまく使いこなせていない」問題が根深いです。
- 画像をアップロードしたらレイアウトが崩れた
- 文字装飾の仕方がわからない
- プラグイン(※追加機能のようなもの)が勝手に動いている気がする
こうなると、触るのが怖くなります。
とくに、制作会社からの引き継ぎが曖昧なままだと、HTMLやCSSの変更が必要な箇所がブラックボックス化し、「専門家じゃないと無理」と思い込んでしまいます。
これは、CMSという便利な道具が、逆に“使えないまま放置される元凶”になるという皮肉な結果を生んでいるのです。
■ 本音6:「効果がある気がしない」から、動機が湧かない
最後に、もっとも根深い理由の一つ。
「ホームページを更新しても、問い合わせが増えるわけでもない」
「更新してもしなくても、売上は変わらない」
こう思ってしまうと、更新の意味自体が見失われます。
しかしこれは、“短期的な視点”に囚われていることが原因です。
ホームページの更新は、検索エンジン対策(SEO)や信頼構築において、大きな意味を持っています。
たとえば、情報が半年以上更新されていない医院と、毎月お知らせが出ている医院──。
あなたが患者だとしたら、どちらに信頼を感じるでしょうか?
■ 「更新が止まる理由」を整理してみると…
ここまでをまとめると、ホームページの更新が止まる理由には以下のような構造があります:
| 要因 | 具体的な本音 |
|---|---|
| 情報不足 | ネタがない、何を書いていいかわからない |
| 優先順位の低さ | 本業が忙しくて後回しになる |
| 手間の多さ | 外注への連絡やCMS操作が面倒 |
| 意欲の欠如 | デザインが古い、やる気が出ない |
| システム問題 | CMSが使いづらい、管理がブラックボックス化している |
| 効果不信 | 更新しても意味があると思えない |
どれも「担当者が悪い」のではなく、「仕組みの問題」「設計の問題」に近いといえます。
■ 更新が“継続される”仕組みとは
- 更新ルールが明文化されている
→「月1でニュース更新」「イベント後に必ずレポート掲載」など、ルールがあると行動が生まれる - 運用担当が“情報収集役”と“発信役”に分かれている
→1人で全部やろうとすると無理がある。役割分担がカギ。 - 更新が“外注化”されている
→更新の手順、ネタの抽出、公開作業まで委託されていると、滞りが少ない - 定例ミーティングがある
→月1で「今月更新すべき内容」の確認をするだけで、見落としが減る
■ ホームページの“価値”を眠らせないために
更新されないままのホームページは、まるで“シャッターの閉じたお店”と同じです。
それが悪い印象を与えるとは限りませんが、「選ばれる理由」にはなりにくい。
一方で、定期的に更新されているホームページは、「動いている感」「活発な印象」を与えます。
企業でも、医療機関でも、士業でも──更新が信用に変わるのです。
だからこそ、「更新できない自分を責める」のではなく、
更新しやすい仕組みや外部リソースの活用を考える方が、はるかに建設的です。
■ 最後に──「更新代行」はあくまで“入口”かもしれない
この記事を読んで、「自分もそうだ」と思った方は、無理にすぐ改善しようとしなくて構いません。
ただ、「ホームページの更新を止めること」は、“放置”ではなく“戦略”であってほしいのです。
そして、更新が続けられる仕組みを持つことは、
将来のホームページの全面リニューアル、事業拡大に向けた戦略設計への第一歩にもなります。
更新は、ただのお知らせ作業ではありません。
それは「企業と顧客の関係性」を形にしていく、大切な営みなのです。